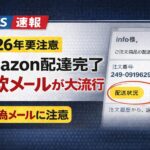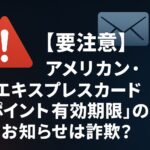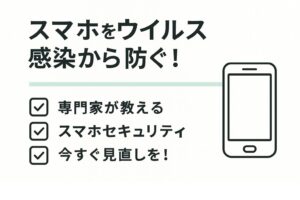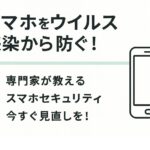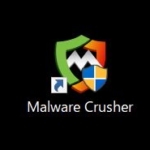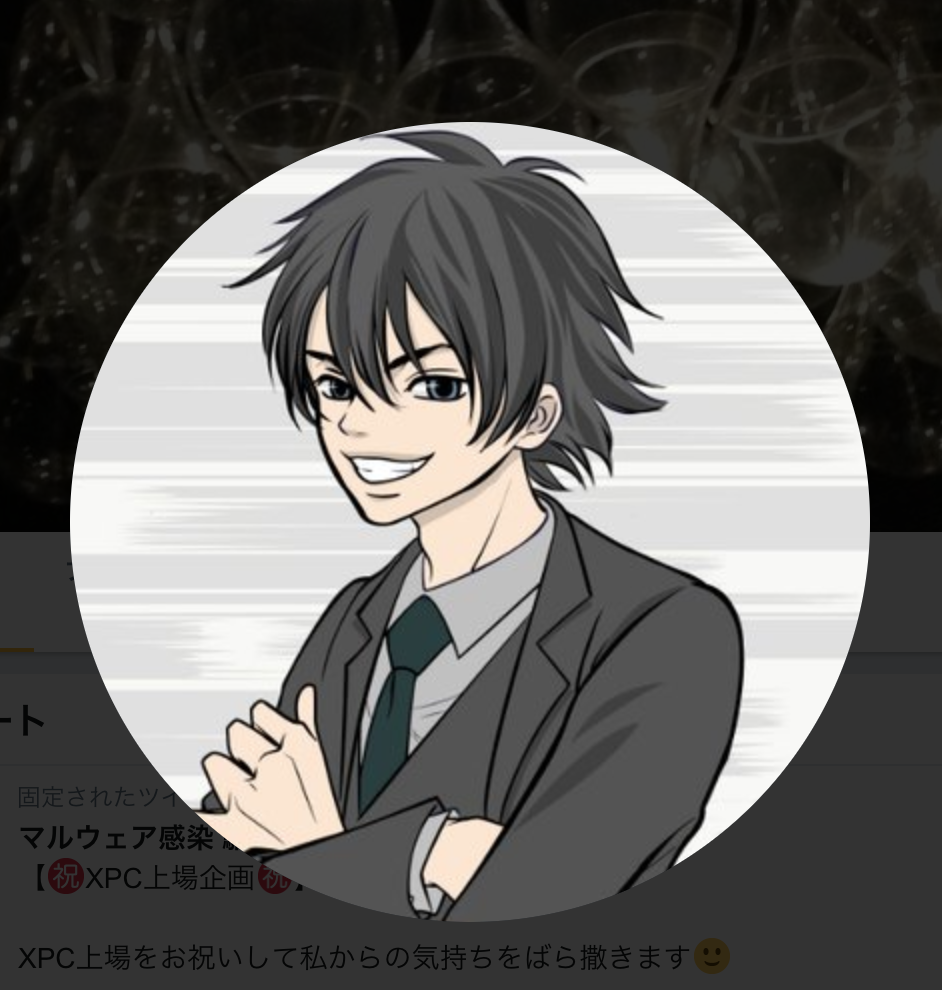サイバー攻撃は年々巧妙化し、2025年以降、国内企業の被害リスクがさらに高まると予測されています。攻撃の対象は大企業に限らず、サプライチェーンを通じて中小企業にも拡大しています。情報漏えいや業務停止が発生すれば、経営への打撃は計り知れません。
本記事では、IPA(情報処理推進機構)の最新データをもとに、サイバー攻撃の現状と企業が取るべき実践的な対策を解説します。さらに、万一の損害に備える「サイバーリスク保険」など、経営層が検討すべきリスクマネジメント手段についても紹介します。
企業が直面するサイバー脅威の現状
現代の企業は、デジタル化の進展に伴い、ますます複雑化したサイバー脅威に直面しています。業務の多くがオンラインで行われるようになったことで、サイバー攻撃のリスクも増大しています。サイバー攻撃はもはやIT部門だけの問題ではなく、企業全体の経営課題として位置づける必要があります。デジタル化が進む中で、取引先・顧客・外部システムとの連携が拡大し、一つの侵入経路が連鎖的な被害を引き起こす可能性があるためです。
「セキュリティは技術部門の責任」という考えはすでに時代遅れです。システム更新、人材確保、教育投資はいずれも経営判断の範疇にあります。経営層が自らリスクの全体像を把握しなければ、対策は機能しません。
アサヒビールの事例から学ぶ ランサムウェアによる業務停止のリスク
ランサムウェア(Emotet)は、企業のデータを暗号化し、復号のために身代金を要求する攻撃手法です。この攻撃は企業の運営に直結する重大な問題を引き起こします。特に、重要なデータやシステムへのアクセスが制限されることで、業務が停止し、経済的損失が発生するリスクがあります。
ランサムウェア(身代金要求型攻撃)は、企業システムを暗号化して業務を停止させ、復号と引き換えに金銭を要求する手法です。近年は「二重脅迫型(暗号化+情報流出の脅し)」も増えており、単なるバックアップ対策では立ち向かえないケースが増えています。
アサヒHDは、2025年9月29日に社内システムへのサイバー攻撃を受けたと発表されました。 同社は後に、障害原因はランサムウェア侵入による可能性が高いと発表しています。
この攻撃により、国内における受注・出荷・生産・コールセンター等の業務が停止し、復旧のめどは未定とされました。また、攻撃の影響は製品の発売延期にも波及しており、アサヒでは一部商品の発売スケジュールが見直されることが報じられています
2025年10月3日現在、アサヒHDの公式発表では「調査の結果、情報漏えいの可能性を示す痕跡が確認されました。漏えいの可能性のあった内容や範囲については調査中」としています。
ランサムウェア攻撃はその破壊力、被害損害額の大きさから、多くの企業にとって最大の脅威です。
サプライチェーン攻撃の影響で中小企業が狙われる時代へ
サイバー攻撃はもはや「大企業だけの問題」ではありません。攻撃者は、セキュリティ体制の弱い中小企業を踏み台として、大手企業への侵入ルートを確保する戦略を取っています。
攻撃者は防御の弱い中小企業を足掛かりに、大手企業への侵入を狙います。IPAの報告では、サプライチェーンを介した攻撃が増加しており、企業規模を問わず標的化が進んでいます。
「うちは小さいから狙われない」という思い込みこそ、最大のリスクです。
アサヒビールの事例から学ぶ「初動対応の重要性」
このアサヒ事案は、経営視点から見ても、攻撃を受けた際の対応が遅れた場合のダメージがいかに大きいかを教えてくれます。
・業務停止と供給網の混乱
福島工場では物流・生産管理システム停止により出荷を継続できず、対応として紙ベースでの記録運用に切り替えられたという報道もあります。
・復旧の遅れが経営に打撃
障害が長引いたため、10月1日に予定されていた新製品発表会が中止に追い込まれました。
・透明性と調査の負荷
当初は「個人情報流出なし」と発表していたものの、後に調査の進展に伴い情報漏えい可能性の痕跡も示されるようになりました。
・復旧だけでなく信頼回復戦略が必要
単にシステムを復旧するだけでなく、社内外への説明責任、ブランド回復、取引先への保証などが課題として浮上します。
アサヒビールの対応から学ぶべきは、初動スピードの重要性です。異常検知から24時間以内にCSIRTや社外専門家と連携し、ウイルスの封じ込めを図る体制が、被害拡大を防ぎます。
「発生しない対策」よりも「発生後の被害最小化体制」こそ、経営の優先課題です
セキュリティ対策の導入の優先順位
サイバー攻撃の脅威が増加するなかで、企業は「限られたリソースで何を優先すべきか」を明確にする必要があります。この章では、経営層とIT担当者が共通理解を持つための対策の整理と、現実的な実施ステップを示します
まず行うべき3つのセキュリティ基本対策
IPA(情報処理推進機構)は、企業がまず取り組むべきセキュリティ対策として次の3点を推奨しています。
-
システムとソフトウェアの最新化
Windows 10のサポート終了(2025年10月)を控え、古いOSを使い続けることは重大なリスクです。アップデート管理は最優先の防御策です。 -
多要素認証とアクセス権限の適正化
システムの不正アクセスや乗っ取り防止には、ID・パスワードログインに加えた多要素認証の導入が有効です。 -
定期的なバックアップと復元テスト
ランサムウェア被害に備えるには、バックアップデータをオフラインまたは別環境に保管し、実際に復元できるかを検証しておくことが重要です。同じネットワーク内に重要なデータを保管しておかないことが基本です
これらはシンプルですが、被害事例を見ると、どれか一つが欠けていることが多いです。まずはこの3点を「確実に実行する体制」を整えることが、次の高度な対策への前提となります。
従業員のセキュリティ意識向上
多くの企業では、セキュリティ対策を「システム導入=安全」と捉えがちです。しかし、実際に攻撃の突破口となるのは人的要因が大半を占めます。
IPAの調査によると、標的型メール攻撃の約7割が、教育不足や業務の忙しさから、怪しいメールに気付くことができず添付ファイルやリンクをクリックしたことでウイルス感染します。また、退職者アカウントの放置や権限管理の甘さも、内部不正や情報漏えいの原因となります。
定期的なセキュリティトレーニングを実施し、最新の脅威情報を共有することで、従業員が不審な活動を認識し、適切に対応する能力を養うことが求められます。さらに、疑わしいメールやリンクを報告する仕組みを設けることで、組織全体のセキュリティ意識を向上させることが重要です
中小企業でも実践できるセキュリティ管理の仕組み
「人員も予算も限られている」という企業でも、最低限の管理体制は構築できます。まず、情報資産を分類し、「何を守るべきか」を明確にしましょう。その上で、責任者を定め、インシデント対応手順を社内に共有しておくことが重要です。
また、IPAの「サイバーセキュリティお助け隊」サービスなど、公的機関の支援を活用する方法もあります。これは専門家が中小企業のセキュリティ課題を診断し、改善策を提案してくれる制度です。さらに、東京海上日動火災など、保険会社で提供されている「サイバーリスク保険」を併用すれば、被害時の調査費用・法的対応・広報支援までカバーでき、経営の安定性を高められます。
| 損害保険会社名 | 商品名・特約名 | 特徴(抜粋) | 公式ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 東京海上日動火災保険 | サイバーリスク保険 | サイバー攻撃の「おそれ」に対応する調査費用も補償。海外での賠償請求も補償対象。 | 商品ページへ |
| 損害保険ジャパン | サイバー保険 | 全世界の事故を補償し、GDPRなどの海外規制に対応。事故発生の「おそれ」への対応費用も補償。 | 商品ページへ |
| 日新火災海上保険 | (各種保険の特約) | 「サイバー・情報漏えい事故補償特約」をセットすることで、サイバーリスクに備える。 | 商品ページへ |
| 大同火災海上保険 | DAY-PRO! 賠責総合保険(特約付帯) | 「サイバーリスクに関する特約」を付帯することで、サイバーインシデントに起因する損害を補償。 | パンフレット(PDF)へ |
| Chubb損害保険 | サイバーリスク保険 | 情報管理、ネットワークセキュリティ、サイバー恐喝など、複数のリスクを多角的に補償。 | 商品ページへ |
これからのサイバー攻撃対策と経営層の責任について
今までサイバー攻撃から防御策は外部攻撃から「社内ネットワークを守る」ことが前提でした。しかし、クラウド利用やテレワークが一般化した今、サイバー攻撃はネットワークの内外を問わず発生します。
つまり、サイバー攻撃を完全に防ぐことはもはや不可能です。これからの経営者には、“攻撃を前提に事業を守る”という発想が求められます。この章では、継続的な防衛戦略と経営リーダーの役割を整理します。
ゼロトラスト時代のセキュリティ思考をもつ
「ゼロトラスト」とは、「社内ネットワークであっても信頼しない」という前提で、すべてのアクセスを検証する考え方です。従来は「社内=安全・社外=危険」という境界型防御が主流でしたが、現在は内部からの侵入・クラウド経由の漏えいが主な脅威です。
ゼロトラストの導入は一気に進める必要はありません。まずは「重要データにアクセスできる人を最小限にする」「ログを自動で記録・監視する」といった小規模導入から始めるのが現実的です。経営層はこの発想を理解し、IT部門に任せきりにせず、自社の情報フロー全体を俯瞰する責任を負います。
リスクを最小化するための「継続的な仕組み化」
セキュリティ対策は一度導入して終わりではありません。脆弱性の発見や攻撃手法の進化に合わせて、運用を継続的に見直す仕組みが必要です。
例)
年1回のセキュリティ監査の実施
システム更新・ソフトウェア管理のチェック(四半期ごと)社員のセキュリティ教育の定期化(標的型メール訓練・異常発生時の報告練習)
これらを定常業務としてスケジュールに組み込むことで、セキュリティ対策の「持続性」が確保されます。また、万一の被害時にはサイバーリスク保険を活用することで、専門調査費・法務対応・損害賠償までをカバーできます。損害保険を組み込むことで、経営判断としてのリスクマネジメントが高まります
まとめ
サイバー攻撃は、もはや“想定外の事故”ではなく、“経営上の必然的なリスク”です。どれほど堅牢なシステムを構築しても、サイバー攻撃手法は進化を続け、完全な防御は存在しません。
重要なのは、地震や津波のように「ハッカーによる攻撃は必ず起こる」という前提で、被害を最小化できる仕組みと判断力を持つことです。本記事を通じて示した通り、最も効果的な対策は“高コストをかけた技術”ではなく、“日常的な管理と意識の継続”にあります。
情報セキュリティ意識向上にむけた5つのポイント
① 経営層が主体的に関与する
セキュリティはIT部門任せでは機能しません。経営層が「企業リスクの一部」として扱い、戦略レベルで管理することが不可欠です。
② 基本的な防御を確実に実施する
OSやソフトの更新、バックアップ、多要素認証といった“地味な対策”こそ、被害を食い止める最大の武器です。
③ サイバー攻撃を受けた後の体制を明文化する
初動対応の遅れが被害を拡大させます。異常検知時の連絡先・封じ込め手順・広報対応を事前に定義しておきましょう。
④ 外部支援と保険を組み合わせる
IPA(情報処理推進機構)の支援制度や、サイバーリスク保険を活用することで、技術的・経済的両面から防衛力を高められます。
⑤ 社員が報告・相談しやすい環境を整える
ここが一番重要かもしれません。情報セキュリティを守る文化は一朝一夕では築けません。普段から従業員の失敗を責めず、報告・相談しやすい心理的安全性を担保した組織風土こそが最大の防御となるでしょう